出張者:森山きよみ・ふじくぼ博文・大森忍・中原ちから・平山タカヒサ

【日程】 2018年1月16日(火)10時~11時
【場所】 京都市役所
【調査事項】 子どもの居場所づくりの取組みについて
【対応者】 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部
子ども家庭支援課長、貧困家庭の子ども対策係長
【調査内容】
(1)事業導入の背景
京都市では、2016年8月に実施した子どもの生活状況等に関する調査などの結果、貧困等の困難を抱える家庭では、保護者が多忙で親子間を含め人間関係が希薄で孤立しており、そのことで子どもの学力や自己肯定感にも悪い影響を与えている実態が明らかとなったことから、2017年3月に「京都市貧困家庭の子ども・青壮年対策に関する実施計画」を策定し、家庭の状況にかかわらず、子どもたちに健やかな育ちを保障するとともに、世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、「すべての子ども、若者が無限の可能性を発揮できるまち・京都」の実現を目指している。
(2)子ども等の生活状況等の実態把握の結果について
① 保護者(母親)の就労状況 (単位:%)
| 正社員・正規職員 | |
|---|---|
| アンケート全世帯 | 33.5 |
| ひとり親世帯(母親) | 40.4 |
| 貧困線以下の世帯 | 20.4 |
② 保護者(母親)の帰宅時間 (単位:%)
| 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時以降 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンケート全世帯 | 24.1 | 12.5 | 5.4 | 1.9 | 2.2 |
| ひとり親世帯(母親) | 32.3 | 18.4 | 10.2 | 3.5 | 3.6 |
③ 学校での勉強の成績 (単位:%)
| やや遅れている | かなり遅れている | |
|---|---|---|
| アンケート全世帯 | 9.2 | 1.4 |
| ひとり親世帯(母親) | 13.6 | 8.4 |
| 貧困線以下の世帯 | 13.6 | 6.2 |
④ 子どもの自己肯定感
ア 子育てにかける時間やお金などの優先度 (単位:%)
| 自己肯定感が高い | |
|---|---|
| 小学生調査(平均) | 70.3 |
| うち最も優先すべき | 77.4 |
| 〃 できるなら 〃 | 67.7 |
| 〃 他に優先すべきことがある・わからない | 60.3 |
イ 親との関わり状況 (単位:%)
| 自己肯定感が高い | |
|---|---|
| 小学生調査(平均) | 70.3 |
| うちほぼ毎日 | 79.4 |
| 〃 週に3~4日 | 77.5 |
| 〃 週に1~2日 | 69.1 |
| 〃 月1~2日・めったにない | 63.0 |
⑤ 保護者の相談相手の状況について (単位:%)
| 相談相手がおらず、欲しいと思っている | |
|---|---|
| アンケート全世帯 | 6.7 |
| ひとり親世帯 | 16.3 |
| 貧困線以下の世帯 | 11.6 |
(5)課題を抱える子ども等や保護者への支援における課題
① 子ども等が、保護者との関わりの薄さや、社会経験等の不足等により、他者とのつながりが希薄になっていることや、生活
習慣の乱れや学習状況の遅れ、自己肯定感の低下等の課題を抱えている。
② 保護者が多忙な生活の中で時間のゆとりがない、保護者自身が知識・経験が不足していることなどから、子育ての不安や負担
感を抱えながら孤立の状況に置かれている。
5 京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金
(1)事業目的
平成29年度から貧困等による困難を抱える子供たちが、放課後等における食事や学習などを通して、大人や地域とつながることで、安心して過ごせる居場所づくりを進めることにより、子どもたちの孤立を防止し、健康や生活習慣の向上を図ることを目的に、子ども食堂や、学習支援、生活支援等、「子どもの居場所づくり」に新たに取組まれる団体等に対し、初期費用の一部を補助するもの。
(2)事業概要
対象経費の総額の2/3以内(上限10万円)
(3)対象事業
① 食事を提供する事業
② 学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のために、自主学習を支援する事業
③ 子どもへの生活支援や社会体験の取組など、趣旨に合致する事業で京都市がみとめるもの
(4)事業規模
① 予算規模 150万円
② 募集規模 15団体
③ 募集実績 15団体(平成29年度)
【所感】
昨今、子どもの貧困問題が取りざたされる中、子ども食堂や学習支援等、民間を中心に行われるようになってきた。本市においても、平成29年6月14日現在、13団体程度が子ども食堂を行っていると仄聞する。
このようななか、「子どもの居場所づくり」に新たに取組む団体に対して、初期費用の補助を行うことは、行政としての姿勢を示すことにつながり、評価に値する。
一方、運営団体からは、運営費用についての相談も寄せられているとのことであったが、運営費の補助については、京都府において行っているとのこと。
運営を行う団体の地域への偏りなど、課題もあると思われるが、子育て支援を行う団体に対して行政として支援を行うことで、より効果的・効率的な「居場所づくり」が図られ、本市としても参考にすべきと思われる。
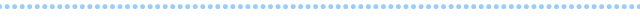

【日程】 平成30年1月17日 午前9時30分~午前10時30分
【場所】 金沢市役所
【調査事項】 金沢市ひとり親家庭等自立支援計画について
【対応者】 児童家庭相談室長、福祉総務課家庭福祉課長、福祉総務課主任主事
【調査内容】
(1)金沢市のひとり親家庭の現状
| 世帯数 | |
|---|---|
| 18歳未満の子どもを養育する世帯 | 42,926 |
| 母子家庭 | 3,173 |
| 父子家庭 | 469 |
※平成27国勢調査結果
(2)計画の概要
≪計画の趣旨及び取り組み≫
・母子家庭及び父子並びに寡婦福祉法12条に規定する自立促進計画
・母子家庭、父子家庭及び寡婦に対する総合的な支援を図る
・施策の事業評価、アンケートでの実態調査、策定委員会のご意見を基に策定
≪計画対象及び期間≫
・母子家庭、父子家庭、寡婦
・平成29年~34年まで(第三期計画)
参 考:平成19年 第一期計画策定
平成24年 第二期計画策定
平成29年 第三期計画策定
(3)アンケート調査結果

(4)計画の主な施策
① 地域派遣型学習支援モデル事業
≪趣旨・目的≫
貧困の状況にある子どもたちへの学習の支援や、自分に自信を持てるような他人との関わりは、貧困の連鎖を断ち切るためにはとても重要。子どもたちにとって身近な地域の集会場にボランティアを派遣する形の学習支援を実施。
≪概 要≫
対象者:ひとり親家庭、養育者家庭の中学生または小学校高学年(4~6年生)
会 場:地区の集会所
実施頻度:月2回
支援方法:大学生ボランティアによる支援
② ひとり親家庭集中相談窓口
≪目 的≫
8月の児童扶養手当現況届受付期間に、ひとり親家庭が抱える様々な課題について集中的に相談できる場として各種相談会を実施
≪内 容≫
・就労相談、養育相談、弁護士による無料法律相談、児童扶養手当現況届受付
実施日:平成29年8月6日(日)、19日(土)9時から15時
参 考:児童家庭相談室のパンフレット

(5)庁内連携の状況
≪子どもの貧困対策の推進≫
・平成28年6月「金沢市子どもの貧困対草チーム」を設置 子供の教育・福祉・健康・就労等に関係する庁内15の課・所で構成
| 関係課(所) | 関係施設・課題等 | |
|---|---|---|
| 福祉局 | 福祉総務課※事務局 | ひとり親家庭の支援、児童手当・児童扶養手当の支給 |
| 生活支援課 | 生活保護、生活困窮者自立支援、子どもの学習支援 | |
| こども政策推進課 | 就学前教育・保育の提供、児童館など子どもの居場所づくり | |
| 子ども総合相談センター(児童相談所) | 児童虐待対応、社会的養護 | |
| 障害福祉課 | 保護者または子供の障害に対する支援 |
| 関係課(所) | 関係施設・課題等 | |
|---|---|---|
| 保険局 | 健康政策課 | 医療費助成、子どもの健康増進 |
| 福祉健康センター | 妊産婦・育児の相談、ひきこもり支援 | |
| 医療保険課 | 国民健康保険による医療の提供、保険科滞納家庭の対応 |
| 関係課(所) | 関係施設・課題等 | |
|---|---|---|
| 教育委員会 | 教育総務課 | 就学援助、入学手続き・学齢簿管理による子どもの状況把握 |
| 学校指導課 | 子どもの学力向上及び学校政策への支援 | |
| 生涯学習課(家庭教育振興室) | 家庭における教育力向上への支援 | |
| 研修相談センター | 不登校や教育等に関する相談、教職員研修の実施 |
| 関係課(所) | 関係施設・課題等 | |
|---|---|---|
| 経済局 | 労働政策課 | 保護者および若者の就労支援 |
| 市民局 | 人権女性政策推進課 | 女性・DVの相談、子どもの権利擁護 |
| 都市整備局 | 市営住宅課 | 市営住宅の供給、家賃滞納家庭の対応 |
【所 感】
ここ数年、日本の経済・雇用情勢は緩やかな回復傾向にあるが、ひとり親家庭を取り巻く状況は、依然として厳しく、ひとり親家庭の約半数が貧困の状況にあると言われており、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることや、貧困が世代を超えて連鎖することが懸念されている。このような状況を踏まえ今回の調査を行った金沢市おいては、「金沢市ひとり親家庭等自立支援計画」を平成19年に策定し、各種施策を展開し、現在計画の3期目に至っている。今回の3期目においては、先に述べたような社会情勢を踏まえ、新たに、ひとり親家庭の貧困対策を柱に盛り込み取り組みを推進し、ひとり親家庭の子どもたちへの切れ目のない支援の充実を図ることを目的としている。注目すべきは、これまでの積み重ねによる施策の事業評価、アンケートでの実態調査や庁内15課による連携体制である。本市においても、平成29年12月に、「子どもの生活に関するアンケート調査報告書」が取りまとめられている。その中で、子どもの貧困対策も重要な施策の要素となりえる可能性が高いことから、参考になる面が多々あった。
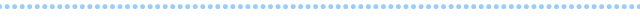
【日程】 平成30年1月17日 午前10時30分~午前11時30分
【場所】 金沢市役所
【調査事項】 金沢市外国人旅行者受入環境整備事業について
【対応者】 観光政策局誘客推進室室長
【調査内容】
1.金沢市の観光施策について
入込客数は、平成27年3月に新幹線の開業。開業前800万人あったものが、開業後には1000万人。平成28年も、入込数は微増している。ホテルも建設ラッシュ、稼働率も上がっている。ただ、もともとキャパが小さい街なので、観光客が増えすぎて、市民生活に支障が出てきている。
例えば、近江町市場では、土日がお客様で一杯になって、地元のお客さんが買い物できない、魚を扱っているお店はもうかりますが、八百屋さんや花屋さんは、つぶれている店もある。
◎「観光立国ショーケース」の選定
金沢市は平成28年1月に、観光庁の観光立国ショーケースという、モデル都市に立候補し認定を受けた。これは東京オリンピック・パラリンピックに向けて、訪日外国人旅行者4000万人という政府の目標がありますが、地方に誘客をしていく、そういう事業をしていくモデル都市に、平成28年1月29日選定、2月16日認定。訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースとして金沢市・長崎市・釧路市の3市を選定。今後は、「観光資源の磨き上げ」「ストレスフリーの環境整備」「海外への情報発信」等に関係省庁が集中支援。
国内外の入込観光客数。外国人旅行者が非常に急増している。金沢市も台湾・中国・韓国・香港などアジアの方々が多いが、ただ最近は欧米系の方々が非常に多くなっていて、平成27年から28年の伸び率では、イタリアが71.9%の増、「なんで金沢を選んだのか」という問いに対しては、「歴史・文化、街並みというものが、ヨーロッパとにている。」ということだ。
金沢市は、毎年、一度、国内及び外国のお客様に、観光動向のアンケート調査を行っているが、傾向としては、体験をされる外国人の方々が、日本人に比べて非常に多いことと、体験時間も3倍ぐらい違う。移動も国内の方々はバス、タクシーなど公共交通を使った移動が多いのに対して、外国の方々は、歩いて移動される方々が非常に多い。外国の方々が求めるニーズと、金沢の歴史・文化・食と合致をしているのかなあと思われます。
現在、イタリアに向けて、ターゲットを絞った誘客をしている。今年の4月にJNTOのローマ事務所を開設しますので、そこに一人、女性職員を派遣しました。去年はミラノ、今年はローマですが、HISという旅行社と現地の支店と組んで、金沢の魅力を発信するような観光プロモーション、去年はミラノに市長が直接出向きまして、セールスを行った。
◎「海外プモーションの推進」
・イタリアを重点市場として、スペイン、フランスの3ヵ国で現地の旅行会社と連携し、旅行商品化を推進
・大手インターネット関連会社と連携し、イタリアへターゲットを絞ったWeb動画プロモーションを実施
金沢にミラノから直接行くというツアーではなくて、東京、箱根、鎌倉、名古屋、高山、京都、大阪といった、コースの中に、金沢を組み入れてもらうといった商品を、たくさん増生していただけるようになった。
◎「広域観光の推進」
・ミシュランガイド3つ星評価の年で連携し、広域観光ルートを開発・PR
・北陸・飛騨・信州 「3つ星街道」
・【高速乗合バス高山線】
平成25年1月―毎日3往復が平成28年4月には、毎日10往復、乗客の6~7割が外国人
三ツ星街道、金沢の兼六園、飛騨高山の白川村、松本市の松本城、この広域で協議会を作り、
官民一緒に、協議会を作って、ここを北陸の周遊ルートとする取組みを行っている。
2.金沢市外国人旅行者受入環境整備事業補助事業の概要
① 目 的
北陸新幹線金沢開業により増加している外国人旅行者が安心して市内観光を楽しめるように、民間事業による外国人旅行者の受入のための整備費に対し交付するもの。
② 補助対象事業者
宿泊事業者、観光事業者、飲食店、商業施設
③ 補助金額
事業者に対し、補助対象額の1/2(上限:20万円)
受け知れ環境の整備事業として課題があるのは、21世紀美術館は金沢市のWi-Fi、兼六園に行くと県の施策なのでWi-Fiをつなぎなおさなければならない。4市1村をWi-Fiの一元化、実証実験を今年は、広域ルートで行っている。
又、外国人が増えるなかで、通訳のガイドさんが少ないという課題がある。金沢市では、昨年の平成28年度から、金沢市内であれば、有償でガイドができる金沢市特例通訳案内士の養成を行っており、43人の通訳ガイド、金沢市のエリア内であれば、報酬を得てガイドができる。こういったガイドを要請している。
【所 感】
報告では、平成29年に新幹線効果を検証する会議の大きなテーマは、「国内はいずれ、下火になるだろう。これからはインバウンドに力を入れていくべきだ。」という見解は、驚きでしたし、金沢市の観光戦略は、そのことを基に進められていると実感しました。
その具体的施策として、金沢市特例通訳案内士の育成・活用ということで、平成28年6月、構造改革特別区域計画の認定を受けて、「金沢市特例通訳案内士」の育成を開始(平成28年の合格者43人)
国家資格者「通訳案内士」や地元ボランテイア通訳ガイドと一体的に案内し、多様なニーズへの対応と通訳ガイドの質の確保を行っておられます。
又、従業員の方が英語をしゃべって、外国人の方と会話をしないと、どうしても売り上げにつながらないということで、金沢観光版のスピードランニングを1000枚ほど作り、観光協会に加盟している事業所さんやタクシー、バス事業所さん、また、登録しているホランティアガイド400人に配布をしています。
さらに、総務省の実証実験として、タブレットとかスマホを活用しまして、ボイスパラーという翻訳アプリを受入環境整備の「外国語翻訳用携帯端末」を購入する場合には補助の対象としますということで、外国の方とタブレットやスマホをかいして、外国人の方にしゃべっていただいて、それを日本語に翻訳できる。音声もきます。それによってお互いの会話を通して購買してもらう。こういう実証実験をしているそうです。
現在、金沢市と大阪市と富良野市、成田市、大北町の4地区が採択を受けまして、実証実験をし、現在50ぐらいの事業所さんが参加をしていただいているそうです。
このように、これからは、インバウンドに力を入れる必要性と共に、外国人向けの通訳ガイドやタブレットやスマホを活用して翻訳アプリなど、本市としても導入していく必要性を感じました。
そして、これまで以上に他都市と連携し、受け入れ環境の充実など、本市観光施策が求められています。